登場人物紹介(869年時点の年齢)
ハサン・イブン・ザイド(39)・・ザイド教団の指導者。
ムハンマド・イブン・ザイド(37)・・ハサンの弟。
タナズ・ビント・ハサン(12)・・ハサンの娘。
ムウタッズ・イブン・アル・ムタワッキル(22)・・アッバース朝第13代カリフ。
ムフタディー・イブン・アル・ワースィク(36)・・ムウタッズの従兄で第9代カリフワースィクの息子。ワーシト太守。
アブドゥッラーフ・イブン・アル・ムフタディー(17)・・ムフタディーの息子。
9世紀後半。
アッバース朝の遺産を巡り、3大勢力が鎬を削りあう中東において、第4軸として台頭しつつある勢力が存在していた。

彼らの名はザイド教団。第4代正統カリフ・アリーの子孫のみが正統なイマーム(指導者)であると主張するシーア派の一派であり、特に、アリーの曾孫で、ウマイヤ朝に対し反乱を起こしたザイド・ブン・アリーに忠誠を誓う「ザイド派」の頭目たる「宣教者(ダーイー)ハサン」率いる宗教集団である。

864年に、ターヒル朝支配下であったタバリスターンの地で反乱を起こし独立を達成。867年にはそのときの復讐のために侵攻してきたスライマーン将軍を撃退し、この地の支配権を確立。

だが、ハサンにとっては、彼らのザイドの教えを世に広め、そして自分たちに敵対する異端者たちを駆逐するために、自らの勢力の更なる拡大は急務であり必要不可欠であった。
故に、彼はさらなる驚くべき手段に出ることとなる。
Ver.1.11.0.1(Peacock)
使用DLC
- The Northern Lords
- The Royal Court
- The Fate of Iberia
- Firends and Foes
- Tours and Tournaments
- Wards and Wardens
- Legacy of Perisia
使用MOD
- Japanese Language Mod
- Historical Figure Japanese
- Nameplates
- Big Battle View
目次
前回はこちらから
アッバースとの同盟
869年5月22日。
ザイド教団とスライマーン将軍との戦いが終結してから3ヶ月後。
教団の首都ザンジャーンの礼拝堂にて、一人待つ「宣教者」ハサンのもとに、一人の男を連れた弟のムハンマドが現れる。

「兄さん、兄さんのご希望の人物を、連れてきたよ」
ムハンマドの背後から姿を現したのは、実に驚くべき存在であった。
彼の名はムフタディー。アッバース朝の第9代カリフ・ワースィクの息子であり、現(第13代)カリフのムウタッズの従兄にあたる。当然、スンナ派を奉じており、本来であればザイド教団の長・ハサンやムハンマドとは激しい対立関係にあるはずの男である。

だが、彼はここに来るだけの理由があった。そしてそれが、ムハンマドが彼を連れてきた理由であった。
「貴公がザイド教団の長、『宣教者』ハサンか。思ったよりも普通だな」
ムフタディーは言いながら、咳き込む。すぐさま脇の側近がその体を支える。ムフタディーは見るからに体調が悪そうで、できたばかりと思われる傷が生々しく光っていた。
「お座り下さい、殿下」

ハサンに促され、ムフタディーは用意された敷物の上に座る。いつもとは比べ物にならない兄の丁寧さにムハンマドはやや驚くが、その兄のムフタディーを見据える双眸の鋭さはいつも通りであることにすぐさま気づく。
そして、ムフタディーの方もそれに気が付いたのか、慎重に言葉を選んでいく。
「この度は、招待頂き感謝申し上げる。既に、我々側の要望は伝わっているだろう。貴公も、同様に我々のような存在を探していたと聞いておるが――」
「ええ、その通りです。我々は、カリフの傍にあって、カリフに敵対する者を探しておりました」
あえて曖昧な物言いを選んだムフタディーを嘲笑うかの如く直截に告げるハサン。狙い通りムフタディーは見るからに狼狽し、場の主導権をハサンが握り始める。
実際、ハサンの言は真実であった。ムフタディーは父の死後、その弟のムタワッキルが後を継いで以降のカリフの混乱を目の当たりにし、その惨状に辟易していた。彼は何とかしてそのカリフの混乱を治め、あわよくば自らがその地位に就こうと考えていた。

その為には、怪しげな異端の徒であっても、利用できるならば利用する他ない――そのようにムフタディーは考え、そしてハサンが弟ムハンマドに依頼したのも、そういった考えをもつ人物をアッバース宮廷内から探してこい、というものであった。
正直、かなり無理のある要求だったように思う。だが、有能なムハンマドは見事その任を成功させた。そしてムハンマドは、兄が初めからそれが「可能」だと理解していたからこそ、自らを遣わせたのだろう、と確信していた。
「――実に危険な男だ。だが、それゆえにこそ、手を組むだけの価値がある、そう考えることとしよう。
改めて、要求しよう。『宣教者』ハサンよ、私と同盟を組みたまえ。そして共に、現カリフ・ムウタッズを廃し、適切なる秩序をバグダードに確立させよう。
その同盟の証明として、貴公の娘と我が息子との婚約を提案しよう」

全ては、ムハンマドが事前に用意した筋書き通りの提案であった。既に事前にハサンにも伝えており、このやり取りは形式的なものに過ぎないはずだった。
しかし、ムフタディーの呼びかけに、ハサンは即答しなかった。「ふむ」とだけ告げた後、顎の辺りに手を添えつつ、じっとムフタディーを見つめ始めた。
いつものアレだ、とムハンマドは思う。無言で相手の目を覗き込み、まるで相手の心の裡を全て丸裸にしようとするかの如く、視線。ムフタディーが居心地悪そうにし始めるのが、ムハンマドからも見て取れた。
やがて、ハサンは口を開いた。
「婿入りだ」
「は――?」
ムフタディーは、ハサンが何を言ったのかよく聞き取れなかったかのように聞き返した。ムハンマドもまた、正直同じ感想だった。
「婿入りを、条件とする。すなわち、貴殿の息子が私の娘に『婿入り』すること、それが条件だ」
ムフタディーは口をあんぐりと開けたまま、言葉を紡げずにいた。ハサンがいつの間にか丁寧な口調を止め、ぞんざいな言い方になっていたものの、もはやそれが問題にならないくらいの衝撃をムフタディーにもその側近にもムハンマドにさえも与えていた。
「な、何を血迷ったことを・・・」
「血迷ったこと? 果たしてそうかな? 貴殿の家系は預言者ムハンマドの叔父アッバースの血を引く家系だが、我々は預言者ムハンマドの直接の子孫であり、我々の家系に入ることの方が、貴殿らにとっても有益だと感じるが?」
「それは、血筋を重視する貴公らシーア=アリーであればそのように感じるかもしれないが、しかし・・・」
「それを飲めなければ、この話は終了だ。お引き取り願おう」
そう言うとハサンはやおら立ち上がろうと腰を上げ始める。
すぐさまこれを止めようとしたムハンマドだったが、それよりも先にムフタディーが声を挙げた。
「分かった、分かった。貴公の提案を呑もう。我が息子アブドゥッラーフは、貴公の娘に婿入りすることとする。・・・だが、代わりに、私の野望の協力は、必ずしてもらうぞ」

ムフタディーの回答を受け、ハサンは再び腰を下ろすと、満足気に口の端を広げた。
「ええ、約束しましょう。殿下のカリフ位獲得に向けて、我が軍も協力は惜しみません。ただ、現時点の我々では、殿下の軍と力を合わせたとしても真正面からカリフに向かうのでは勝ち目がありません。よって、まずは我々の拡大と成長のために、まずは最初に力を貸してほしいと思っております」
再び丁寧な口調となったハサンだったが、それはムフタディーにとってはより恐ろしい重圧に他ならなかった。
それぞれの成功
ムフタディーの息子アブドゥッラーフとハサンの娘タナズとの婚約が結ばれた1週間後、ハサンは南方のジバールへと攻め込むことを決めた。アッバース朝カリフのためにこの地の太守を務めていたドラフ家が治める土地であったが、アッバース朝の衰退と共に半ば独立し、カリフに対し公然と対立する状況になっていた。


そんな彼らがカリフと戦争状態に入ったことを確認し、ハサンは軍隊を動かした。彼らの兵が領国内のガズヴィーンを通過するタイミングを狙って、奇襲を仕掛けたのである。

兵数においては劣っていたものの、敵兵はまともに給与も支払われていないような寄せ集めの軍隊。士気は低く、ザイドの戦士たちの敵ではなかった。



一度敗走せしめた後、リベンジを狙って再び戻ってきたところを、今度は駆けつけたムフタディーの軍も合流し、撃退。


嫡子ドゥラフもこの戦いで捕らえられたことで、ジバール総督アブドゥル・アズィーズもついに降伏を受け入れ、ハマダーンの地をハサンたちに割譲することに同意した。



もちろん、協力を得たからには、次はハサンたちの番だ。
870年12月26日。
アッバース朝第13代カリフ・ムウタッズが、癌により若くして崩御。

巨大なアッバース帝国の主権者の地位は、わずか9歳のムウタッズの嫡子アブドゥッラーフのものとなった。


この機会に乗じたのがムフタディーである。
彼はバグダードの領有権を主張し、アブドゥッラーフの弟のバグダード太守ハムザに対して宣戦布告。

明らかに横暴なふるまいではあったが、背後にザイド教団の軍事力もある中で、幼君への継承直後の混乱期に、一族全体を巻き込む大内戦を起こすわけにはいかない。

そう考えたサーマッラー*1のカリフは、弟への軍事的な援助を供出すること叶わず、味方のいない中で872年7月1日、ハムザとその側近たちは降伏を宣言。

ムフタディーはワーシトとバグダードの2太守領を手にし、家内最大勢力へとのし上がったのである。

「いやはや、我らの同盟は実に勇壮。そして、宗派の垣根を超えた、実に分かちがたい結びつきであるな」
ハマダーンの宮廷に訪れたムフタディーは、上機嫌な様子でハサンに話しかける。3年前の会談のときの険悪な雰囲気とは打って変わってである。対するハサンも「そうですね」と薄ら笑いを浮かべながら適当に相槌を打っている。
「今や、アッバースの帝国内で我らが最も豊かな土地を持ち、最大の勢力であることは明白。あとはじっくりと内部で賛同者を増やし、数年以内にカリフ位を簒奪してやろう・・・」
ほくそ笑みながら、皮算用を続けるムフタディー。ムハンマドは我慢できず割って入る。
「殿下、帝国内での勢力拡張、実に喜ばしいことかと存じます。しかし一方で、外敵にもまた、注意の目を向ける必要があるかと」
「外敵・・? ああ、トルコ人のことか」
上機嫌に水を差された形となり、明らかに不機嫌な様子でムハンマドのことを見やるムフタディー。
「ええ、その通りです。実際、近年この中東の混乱に乗じ、各勢力が自らの戦争を優位に運ばせる為に外来のトルコ人たちを引き入れ、彼らに土地を与える事例が頻発しております。周縁部のシルヴァーン辺りがトルコに支配されるだけならまだしも、つい最近では我らによって弱体化されたドラフ家が、敵対勢力によってトルコ人たちを招き入れられ、結果として帝国に隣接するエスファハーンが彼らの勢力下に落ちるという由々しき事態が発生しております。奴らの牙は、間も無く中央の権力にまで及び兼ねません」


「貴公の言いたいことも分かる。だが、奴らの故地はあくまでもカスピ海の向こう。こんなアラブの中心にまで進出してきた勢力が、その本来の力を発揮して帝国に立ち向かうことなど、無謀に他ならない。
むしろ、我々が彼らを取り込んでしまう方が十分ありうるだろう。事実、すでに一部のトルコ人たちは宮廷内にて戦士として使われておる。もしもアラブの中のトルコ人たちが、無謀にも帝国に襲い掛かってくるようなことがあれば、同じトルコ人同士で戦わせるなりなんなりして、撃退してみせようじゃないか」
カッカッカッと高らかに笑うムフタディー。ムハンマドはちらりと兄の横顔を盗み見るが、変わらぬ微笑を浮かべたまま特に何も言おうとしない彼を見て、ムハンマド自身も何かを告げることを止めた。
----------------------------------------
「――トルコ人の件、どう思う?」
鬱蒼と茂るナティルの森の中で狩りに勤しむザイド教団の一行。その中で、ムハンマドは隣を歩く兄に尋ねた。
「ああ――奴らは、ハイエナみたいなものだな」

「ハイエナ?」ムハンマドは聞き返す。
「ああ。奴らは集団で協力し、例え相手が自分たちより弱い存在であろうとも、すぐには攻撃を仕掛けない。どんな弱者でも、強力な反撃を仕掛けてくることがあると知っているからだ。
代わりに奴らは執念深く獲物を追いかけ続ける。そしてやがて一部の獲物が疲れて群れから脱落したときに、いよいよこれに飛び掛かるのだ」
そのとき、狩りを主導する狩猟頭のワーヒドが、一同を呼び止めた。どうやら、いつの間にか我々は、ハイエナの一群に取り囲まれていたらしい。

「そうしたら、どうするんだ?」
「決まっている」
ハサンは傍らの従者から槍を奪い取り、自らこれを構え、ハイエナの一群の中でも特に動きが緩慢なものを見つけると、そこに穂先を向けた。

ムハンマドが止めようとする間もなく、ハサンは一気に獣との間合いを詰め、これに槍を突き刺した。

見事な一撃。そのあまりにも鋭く強烈な一撃で、獲物となったハイエナが一瞬で息絶えたのはもちろん、その周囲にいた残りのハイエナたちも、一目散に逃げかえり、一同は危機を脱することとなった。
誰もが驚きつつも、さすが宣教者様だ、と口々に誉め称え、拍手する。

「ある意味で、我々も同じことをすればいい。奴らは我々を囲み、追い立て、狩りの機会を窺っているかもしれないが、逆に我々がその機会を狙って動いている――少なくともそういう奴がいる――ということに気が付いていないのだ。
ほら、これをやろう、ムハンマド。今は単なる牙だが、本当の狩りの成功の暁には、もっと大きなものを渡してやるぞ」


珍しく嬉々とした表情で戦利品をムハンマドに手渡してくるハサン。礼を言いつつ、ムハンマドはどこか一抹の不安を覚えていた。
もちろん、不安に思う必要などない。ハサンはいつだって正しく、彼の前にある道には勝利しかないのだから。
最期の時
872年夏。
兼ねてより続いていたサッファール朝との戦争に敗北したターヒル朝はその領土の多くを喪っていた。さらにその状態のターヒル朝に対し、まさにハイエナの如く、東方のゴール朝、北方のアフリーグ朝といった勢力がその脇腹を突き、少しずつ領土を奪っていったのである。
もはや、ターヒル朝はかつての権威を喪い、虫の息となっていた。

この状況を見て、ハサンはすぐさま行動を開始した。4年前に誓った復讐を果たす、絶好の機会であった。

アルボルズ山中で繰り広げられた激戦では、ついに宿敵スライマーンの首を、ロスタムの手によって討ち取ることに成功。


そのままスライマーンの旧領をすべて制圧し、874年1月28日にはアミールと講和。


奪い取ったゴルガーンの地には、人質として手元に置き続けていたスライマーンの嫡子イスマーイールを領主として据え置くこととした。


ハサン自らザイド派の教えを説き込み、信奉するようになった彼は、この地をこれからもよく治めてくれることとなるだろう。

順調に勢力拡大を進めていたハサンたちのもとに、その報せが届いたのはその年の暮れであった。
「オグズ、キルギス、キメクといったトルコ人たちが次々と襲来。帝国の国境線を破り、侵入してきております! その数、1万超!」



恐れていたことが起きた。
急使と同じ焦燥感を味わいつつハサンを振り返ったムハンマドは、そこでいつもの涼し気な顔で佇む兄の姿を見た。
「何をそんなに慌てている? 予想できていたことなのだろう?」
波が引くようにして、焦りが身から消えていくのを感じるムハンマド。
「そうだな・・・その通りだ。戦士たちはいつでも戦える準備をせよ! 但し、まだ動きはしない。密偵を東西に遣わし、トルコ人たちの動きを探ることに集中させよ。たとえ奴らが帝国内に侵入したとしても、指示があるまでは動かないよう、各司令官に厳命せよ」
ムハンマドが遣いに出していく指示を聞きつつ兄が頷いているのを見て、ムハンマドは心から安心した心地を覚えていた。
そして、875年2月14日。
トルコ人たちが遠い東の果て、アラル海よりさらに東の、天山山脈の辺りにてキルギス人たちと合流しようとしているとの報告が入ったことで、ハサンはついに行動開始を指示した。

無人となったシルヴァーンへと、全軍を派遣。
ただちに、その全領土を制圧せしめる。

恐るべきトルコと戦わずして、勝利を掴む。
その妙手に、ムハンマドは感心する。
しかしそこに、一通の報せが入る。
「トルコ人の一派が、ゴルガーンにて略奪を働いているとのこと。当地の領主イスマーイール様より救援の依頼が来ております」

一瞬、いやな思いがムハンマドの中を駆け巡った。時折そういうことがある。そんなとき彼は、なぜそう感じたのかを理論的に考える癖があった。
今回は、この救援のために現在のシルヴァーン包囲部隊の半分以上を割いたとして、残り半分以下しかいない中にトルコ人が戻ってくれば一溜りもないというリスクがある中で、果たしてかのスライマーン将軍の息子の土地を護るために、そのリスクを取る必要があるのか、ということであった。
次に、彼は傍らのハサンの表情を見ることにしていた。理論で考えた彼の結論は、往々にして兄の直観によって覆されることがある。
今回のハサンの顔は――なぜ行かないのか? とムハンマドに問いかけるような表情であった。
その瞬間、彼の言うべきことは決まった。
「最低限の攻城部隊を残し、残りはゴルガーンの救援に向かわせろ。全速力だ!」
そして875年夏。ゴルガーンを略奪中のトルコ人(オグズ人)部隊に対し、ハサン率いる精鋭1,200で強襲する。

戦いは、一方的であった。世に聞くトルコ人の強力な弓騎兵もいたようだが、その数は少なく、ザイドの戦士たちの敵ではなかった。



それは、ムハンマドにとって誇りであった。
この「宣教者」ハサンと共に歩めば、不可能はない。
すべての正しき道は彼が指し示し、そして我々はそこについていくだけで、勝利と栄光とを得られる。
そう、ハサンは常に正しく、そこに敗北はない――。
「行け! 敵を一人残らず駆逐せよ! 誰一人生かしてこの場を逃がせるな!」
ムハンマドは叫び、右手を振り上げ、そして自ら騎馬に跨ったまま先頭で敵陣へと突っ込もうと駆け出した。
その瞬間――
「サギール様――!」
ムハンマドを呼ぶ声が聞こえると同時に、視界の隅にこちらに向けて弓を弾くトルコ人の騎兵の姿が映った。
しまった――という後悔が、体を正しく動かすという結果に繋がるより先に、放たれた弓矢がまっすぐと自分の眼前に飛び込んでくる姿だけがはっきりと映った。
気が付けば、ムハンマドは空を見上げていた。
遠くの方で、味方が勝鬨を挙げている声だけが聞こえた。
ムハンマドに覆いかぶさり、何事か叫んでいる仲間たちに向けて、彼は絞り出すようにして尋ねる。
「我々は・・・勝ったのか・・・? 兄は・・・ダーイーは無事か・・・?」
仲間たちが何と言ったのか、はっきりとは分からなかったが、しかし霞む視界の先でどうやら頷いているらしいことだけは理解し、ムハンマドは心から安心したように、笑顔でその43年の生涯に幕を閉じた。
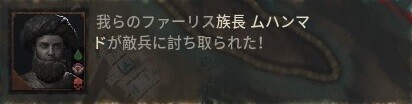
876年1月14日。
シルヴァーンの地を完全制圧したハサンは、この地を不当に支配していたトルコ人のコルプチを降伏させ、シルヴァーンの全ての領土をザイド教団領に編入した。


この勝利の報せを、家令のザハクから受け取ったハサンは、彼に尋ねた。

「ムハンマドは、いないのか? いつもなら彼が報告してくれるはずなのだが」
ハサンのその言葉に、ザハクは一瞬の躊躇いを見せたあと、答えた。
「ダーイー、残念ながら、弟君は・・・」
その言葉を聞いても、ハサンの表情は変わらなかった。
ただ、沈黙し、暫しの時を経たのちに、いつも通りの冷静な響きでただ一言、呟いただけであった。
「そうか、分かった」
第3回「ペルシアの遺産」へと続く。
「その頃のヨーロッパ」はこちら
アンケートを作りました! お気軽に投票・記載ください!
過去のCrusader Kings Ⅲプレイレポート/AARはこちらから
*1:この時期、一時的にバグダードからサーマッラーに首都が移転されていた。