19世紀日本。
2世紀以上にわたり続いてきた徳川家による統治は今まさに終わりを告げようとしていた。
破綻へと向かう財政を持ち直そうと、新たに老中首座に任命された水野忠邦は「天保の改革」と呼ばれる一連の財政再建策を開始。

しかし農民に対しても過酷な年貢率を課したこの改革は、やがてこの国最初の「扇動者」寺内護久を生み出すこととなる。

寺内は幕府の要職についていた農政家・二宮尊徳の協力を得つつ革新的な改革である「地租改正」を実施。

その後も数々の改革を推し進め、日本は次第に近代化の道を進んでいくこととなった。


さらに19世紀半ばになると、ロシアによる南下政策に脅威を感じた彦根藩主・井伊直弼が幕府の実権を握り、老中に任命した若き才能・小栗忠順と共に更なる改革を断行。



その果てにはついに「開国」を決断し、半ば隠居状態であった寺内の力も借りて、1862年12月にこれを実現した。

だが、天皇の勅許なく諸外国と条約を結んだことに保守派の怒りを買い、翌1863年3月に桜田門外で井伊直弼は暗殺。
分裂しかかった幕府と朝廷、雄藩たちの仲をとり持つため、1863年7月に京都にて小栗と各藩の有力者たちが一堂に会することとなった。
その「二条会議」の場で、小栗はとある劇的な改革について提案する。
それは、これまでのような譜代大名を中心とした幕政でもなく、島津久光が提案するような一部の雄藩が主導権を握る幕政でもなく、国民が自ら、自分たちの意見の代表者を選出し、これが集まって幕政を担う「参与会議」を形成するというもの。
国民に被選挙権はなく、代表者となりうるのは幕府・朝廷・雄藩が推薦した者たちだけではあるものの、投票権は一定の財産制限と男性であることのみが条件となる、実に開かれた先進的な選挙制度であった。

1866年3月に最初の選挙が行われ、小栗ら幕府の中枢を担う「開国派」が見事勝利。

民主主義の担い手として小栗および幕府の権威も回復し、徳川幕府は何とか、その命脈を保つことができそうな状況となっていた。
しかし、時代の変革の瞬間というのは、その中心にいる者たちを例外なくその濁流に飲み込んでしまうほどの勢いを持っている。
すべてがうまくいったという革新ほど脆いものはなく、やがてそれに関わった改革者たちはもれなく新時代の肥やしとなってしまうだろう。
小栗もそれは十分に理解していた。
理解しながら彼は、止まることなく突き進むことを決意した。
彼もまた、時代の波に飲み込まれた一人の「改革者」であったのだ——。
Victoria3プレイレポート/AAR第15弾「日本」編第2回。
史実とは異なる「日本史」は、その歩みをさらに加速させていく。
Ver.1.3.6(Thé à la menthe)
使用DLC
- Voice of the People
使用MOD
- Anbeeld's Revision of AI
- Cities: Skylines
- Compact State Overview
- Declare Interests Button on top
- Dense Market Details
- Dens Trade Routes Tab
- ECCHI
- Extra Topbar Info
- Historical Figures
- Improved Building Grid
- Japanese Language Advanced Mod
- Japonism
- More Navy Illustrations
- More Spreadsheets
- Romantic Music
- Universal Names
- Visual Leaders
- Severe Malaria Icon(Edit)
目次
第1回はこちらから
忠誠の宛先
慶応2年9月(1866年10月)。
老中首座・小栗忠順は、70名を超える大規模な使節団を引き連れて英国・ロンドンを訪れていた。
「老中首座自ら海外視察に出なくとも」と幕府内では異論も出たものの、小栗は自らの目と足で外国を知りたいと言って聞かず、後を老中・板倉勝静に任せて旅立ってしまったのだ。
「江戸城に引きこもっているだけでは、改革への道を進むことはできない。寺内殿がそうだったように」
小栗はこの春に没した盟友・寺内護久のことを思い返しつつ、いよいよ波間の向こうに姿を現した異国の地の勇姿をその目でしっかりと焼き付けた。

「どうですかな、我らがロンドンの地は。少しは参考になるものはありましたか?」
ダウニング街10番地の応接室へと通された小栗に、遅れて部屋に入ってきた英国首相ライオネル・ド・ロスチャイルドは誇らしげに告げた。

「実に素晴らしいですね。とくにあのびっぐべんとかいう巨大な建造物・・・あんなもの、我が国にはどこを見渡しても見当たりません。貴国の技術力と科学力には驚嘆するばかりです」
「お褒めに預かり光栄です、ミスター・オグリ。しかし私も日本の風景の美しさには惹かれるものがあり、ただ巨大なだけ、強いものだけではない、小さきもの、かよわきものを愛でるその思想には共感致します」
「ほう、まことですか」
「ええ、私の所有するロンドン近郊の公園には、日本庭園も造らせております。ぜひのちほど、ご覧いただければと思います」
紳士的なロスチャイルド首相の会話術に小栗も魅せられる一方、その言葉の端々に垣間見える小栗の聡明さにも首相は気づき、敬意を表し始める。すぐに二人は往年の親友同士のように打ち解けるようになった。
「然して、ロスチャイルド殿。此度の目的である日英の修好通商の議の改正批准書をば・・・」
「おっと、そうでしたな。つい会話が弾んでしまい」
そう言うとロスチャイルド首相は、傍らに座る秘書の持つ鞄から一枚の書類を取り出した。
「内容について、ご確認ください。これは単なる通商の議ではなく、今後の我々の関係をより一層強固なものとするための、一種の同盟締結と思っていただければと思います」
差し出された紙にはぎっしりと英文が並んではいたが、それを小栗は通訳も介さず自らの目で隅々まで読み進める。
そこには確かに、日本と英国の対等な関係に基づく貿易協定締結を意味する条文が並んでいた。それは事前に説明されていた内容と合致するものであり、天皇陛下の勅許をすでに得ていたものであった。

「問題ないでしょう。この内容で、締結させていただきます」
小栗は傍らの外交官・村垣と共に最終確認の上、条文の末尾に自らの名前をサインした。
「ありがとうございます。これで我々と日本とは、極東の安定を保つための重要な同盟関係を結ぶことができます。共に、ロシアの脅威に対抗していきましょう」
小栗はロスチャイルド首相が差し出した右手を握り返し、満足気にほほ笑んだ。
「ところで、ミスター・オグリ」
すべての定められた段取りを終え、いよいよ切り上げようとした小栗に、ロスチャイルド首相が最後に質問を投げかけてきた。
「私はいまだによく理解できない、しかし実に興味深い日本の制度があるのです」
「ほう、なんでしょう」
「それは、日本の支配者は一体だれなのか、ということです。日本のエンペラーは天皇と呼ばれる一族であることは理解しています。これは驚くべきことに千年以上に亘り途絶えることのない系譜において日本を支配しております。それは私たち欧州の王室にはありえない長さを誇る、驚異的なものです。
一方で、ミスター・オグリ。貴方の主君であるトクガワもまた、日本の支配者であると理解しております。トクガワもすでに200年以上に亘り日本の支配者であり続けていますが、これは私たちにもよく理解できるものです。
一体、日本の王は誰なのか? トクガワなのか、それとも天皇なのか?」
何気ないロスチャイルド首相のその問いかけは、しかし小栗にとってもそう簡単に応えられるものでもなかった。傍らの村垣もやや不安気な顔で小栗を見やる。
「・・・失敬、やや配慮に欠ける質問だったかな?」
その反応に驚いたロスチャイルド首相は慌てて言葉を紡ぐが、小栗は微笑しながら頭を振った。
「いえ、その疑問も最もです。貴国の考えでいうところの王というのはわが国で言えば天皇陛下にあたるでしょう。将軍家はあくまでも陛下から大政を委任されているに過ぎません」
「なるほど、少し立場は違うが、我々もまた女王陛下より大命を降下されている身。日本のトクガワと我々は似たようなものなのかもしれぬな」
得心した、という風に頷くロスチャイルド首相。
それを見やりながら、小栗も彼に訊ねた。
「しかし一方で、貴公が述べた通り、我らが主君もまた200年以上に亘りこの国を統治してきた大君であることも事実。もし、その行く末と陛下の思いとが異なる道を辿ろうとするならば、果たして私はどちらにつくべきなのか—―」
小栗の口から飛び出した思いがけぬ言葉に、傍らの村垣は慌てた様子で制止しようとする。
しかしその前に、ロスチャイルド首相が言葉を紡ぐ。
「ふむ――そうですな。我々の国でいうところの議会が、それに近いのかもしれません」
村垣も興味をそそられ、耳を向ける。小栗は真剣な表情でロスチャイルド首相の次の言葉を待った。
「陛下より大命を降下された我々は、責任をもってその政務を全うする。しかしそれは常に一つの集団によってのみなされるわけではない。私たちは保守党と呼ばれる組織を作り、その信念に従って政治を行う。いわば貴方がトクガワに忠誠を誓うようなものかもしれません。
しかしその政治が上手くいかず、困難に直面することもしばしばあります。そのときは議会を解散し、我々は民意に問うのです。貴国も最近導入されたという、選挙という制度を用いてね。そしてその民意が支持した政党が我々ではない政党――たとえば自由党であれば、これを中心とした新たな政権を形作る。
その交代のスパンは王家の交代と比べれば遥かに短く、頻繁ではあるが、この政権に真に正当性を与えるのは女王陛下でも神の御心でもない。我々が最も尊重すべき――民意なのです。
ゆえに、我々が最後に最も忠誠を誓うべき相手は、党でもなければ——不遜ではありますが陛下ですらなく――国民なのではないでしょうか」
-----------------------
日本への帰路。船上で揺れる波間を眺めつつ、小栗はロスチャイルド首相の言葉を何度も頭の中で繰り返していた。
忠誠を誓うべきは将軍家でもなく天皇陛下でもなく――国民。
それは、遠い異国の理解し難い信念、とは到底思えなかった。
その考えはむしろ、あの敬愛する寺内護久が体現した思想そのものであるかのように思えたのだから——小栗はようやく、寺内の改革への強い動機の出所を、真に理解し得たような気がしていた。
ならば、と小栗は思う。
私は国民という真なる主君のために——誠心誠意、尽くさねばならぬだろう。
その決意を形にするかのように、帰国した後の小栗は次々と新たな改革へと突き進んでいった。
まずは地租改正後も武士・大名に有利で百姓を苦しめていた税制をより平等なものへと変える税制改革。

さらに、全国の関所を廃止し、藩をまたいだ移動の自由を全面的に認めるお触れも出したことで、国民の自由を保証すると共により一層国内交易の活性化を促進することとなった。

しかし小栗の懸命な努力虚しく——時代の変革の奔流は、容赦なく彼の運命をも飲み込んでいく。
そして時代は、次なる主役を求めることとなる。
その男の名は平岡宗悦(むねよし)。
新たな時代を形作る、「維新」の士であった。

公議派の隆盛
平岡宗悦は天保元年10月3日(1830年6月1日)、裕福な土佐藩郷士の家に生まれた。
17歳の頃に剣術修行のための江戸遊学を認められ、上京。修行の傍ら、浦賀沖に現れた異国船の威容を目の当たりにしたり、蘭学者・佐久間象山の下で砲術や兵学、蘭学などを学ぶなどして、少しずつ先進的な思想を取り入れていくこととなった。

その後も剣術家として順調に成長しつつ、折を見て積極的に最先端の学問を学んでいく宗悦。やがて30を過ぎた頃に江戸で巻き起こった大老・井伊直弼による天皇勅許なしの開国、及びこれに不満を持った水戸藩士らによる桜田門外の変に衝撃を覚え、やがて尊皇攘夷思想の結社「土佐勤王党」の一員として活動していくこととなる。
慶応元年(1865年)、老中・小栗忠順と「改革者」寺内護久の尽力によって行われた第一回の「参与会議議員選出選挙」において、勤王党は徳川斉昭や島津久光ら「攘夷派」を支援して選挙戦を戦うも、敗北。

政権は開国派によって握られ、彼らにとって都合の良い改革が進んでいく一方となっていった。


一方で、彼ら攘夷派の肝を冷やす事件も発生した。
慶応2年8月10日(1866年9月25日)、攘夷派の急先鋒であった長州藩が馬関海峡を封鎖し、航行中のフランス艦隊に無通告で砲撃を加えるという事件が発生。
その報復として約半月後の慶応2年8月25日(1866年10月16日)、フランス艦隊が大挙して馬関海峡に現れ、停泊中の長州海軍を砲撃し、これに壊滅的な打撃を加えた上で砲台を占拠するという事件が発生した(下関事件)。
この出来事をきっかけにフランスと江戸幕府との関係性は急激に冷え込み、今にもその本隊が江戸湾沖に現れて幕府に攻撃を加えるのではないかと多くの国民が恐怖に震える事態となったのである。

この状況は、同時期にロンドンへと渡っていた老中首座・小栗忠順がイギリスとの友好条約を締結したことにより、イギリスが仲介役を買って出たことで実際の戦争にまでは発展せずに終わった。
この顛末は幕府・開国派の手腕に対する称賛を呼び起こし、彼らの勢いを後押しする手助けとなったのみならず、国家を危うく存亡の危機へと陥れかねない事態を引き起こした攘夷派に対する求心力の低下という結果を招いたのである。
そして平岡宗悦も攘夷派に対する失望と「攘夷」そのものの非現実性に直面し、次第にその思想を変えていくことへと繋がる。
そんなとき、彼は一人の男と出会うこととなる。
男の名は津田真道。津山藩出身で平岡と同じく佐久間象山に学び、蕃書調所に雇用されて開国とほぼ同時にオランダへ留学を経験した男。

彼は帰国後の1866年、留学先のライデン大学における法学の講義録を訳出した『泰西国法論』を出版。日本初の西洋法学の紹介となったこの書物に刺激を受けた平岡はただちに彼のもとへと向かい、その豊富な知識を飽くことなく吸収していった。
その中で平岡は、この国が欧米列強に負けず、より強靭な国となるために必要なことは、何よりもまず精神の近代化・西洋化であることを理解した。
幕府は確かに開国への道を辿り、急速に近代化を果たそうとしている。しかしそこにはまだ旧来の封建制への拭いきれない執着が残存しており、近代的な皮を被った「選挙」においても、あくまでも国民は有力な大名たちの中から限られた数の「代表者」を選ぶほかない古臭い制度となってしまっている。
ここからこの国は変えていかなければならない。国民の真なる代表者たちを「広く」集め「輿論」を喚起し、そこから「公議」――すなわち「議会」を形成していかなければならない。
そう考える「公議派」を、平岡は津田真道や幕府の重鎮でもあった横井小楠らと共に支持し、その勢いは次第に盛り上がっていくこととなった。


それは決して最初から順調な戦いだったわけではない。
1870年に行われた第2回「参与会議議員選出選挙」では、第1回と比べれば着実に議席数を増やすことには成功したものの、まだまだ政策に大きな影響を及ぼすには不足過ぎる状況ではあった。

それでも平岡は自分達の信念と、そこから導かれる「未来」について熱く語り、それが少しずつ、国民の意識を変えていったのである。


そして令徳3年2月18日(1874年3月22日)に開票された第3回「参与会議議員選出選挙」において、ついに「公議派」は第一党に登り詰めるに至った。

小栗忠順ら開国派、島津久光ら攘夷派を差し置いて政治の実権を握った公議派。
彼らは国民に示した「公約」通りに国民の政治参加を促す法令を発布し、国民は新たに自分たちの主義主張を直接幕府に届けるための「政党」の形成へと動いていくこととなる。


それはすなわち、国民の政治参加への道がより広く開けていくことを意味する。
そしてそれは同時に、これまでの「幕府」や「藩」による封建支配の時代の決定的な終焉をも、意味するものとなっていったのである。
御一新
参与会議の主導権を握った公議派ではあったが、一方でこの国はまだ「幕府」が政治の中心であることは変わりなく、その最高権力者は「将軍」であり、それに次ぐ実質的な行政最高位に位置づけられていたのは老中首座・小栗忠順その人であった。
これまではその小栗を中心とした開国派が参与会議も支配していたがゆえに問題は表面化しなかったのだが、これが逆転したことによって、政治の歪みが生じることになる。それは一歩間違えれば内乱に繋がりかねないだけに――公議派のリーダーである津田真道は、とある政治的決断を小栗に突きつけるべく、小栗の居る二ノ丸御殿・御用部屋へと向かっていた。
許可を得て部屋に入ると、そこに座していた小栗はどこか覚悟の決まった表情を見せていた。

「こうして二人だけで話すのは久方ぶりだな、津田殿」
「左様で御座いますな。それこそ—―開国の直前か、それくらいだったかもしれません」
その経歴においては大きく異なる二人ではあったが、蕃書調所で才覚を発揮していた津田に興味を引かれた小栗が自ら声をかけ、同世代ということもあり諸外国の脅威と国家の未来について数多く語り合う時期も存在していた。
その後、より一層多忙を極める小栗と、政治的に少しずつ異なる道を歩み始める津田との間は次第に距離を開いてはいったものの——言葉を交わさずとも、二人の間にはどこか、同じ方向を向いている確信が共に存在していた。
「平岡くんと言ったかな。彼も息災か」
「ええ。相変わらず突飛な思考には我々も驚かされますが——しかし、彼の発想は、私たちにとっても大きな刺激となっております」
「そうか。うむ、そうだな・・・」
頷きながら、どこか小栗は次の言葉を言おうとして逡巡する、そんな様子に津田は気が付いていた。しかし彼は小栗を急かすことなく、彼が自ら言おうとすることをまとめ、口にすることを決断するのを辛抱強く待った。
「私は—―このときが来ることを、予想はしていた」
やがて、小栗は自らに言い聞かせるかのように言葉を紡ぎ始めていった。
「10年前、『選挙』制度を自ら提案したそのときには、この運命は決まっていた。とはいえ、あのときはそうしなければ、あの時点で我々幕府は主導権を失っていたこともまた、事実だ。私はあの選択を間違っていたとは思わないし、多くの幕臣もまた、同じように考えているはずだ」
「ええ、小栗殿のそのときの選択は、幕府の長として最も適切な選択だったと思います」
「一方で、その選択の帰結――すなわち、今この、君たち『公議派』が突き進めようとしている流れもまた、私は決して望まれぬ結末だとは思ってはいない。むしろ私は・・・それを、心のどこかで歓迎さえしている節もある」
言いながら、小栗は10年前、遠い異国の地で与えられた言葉を思い出していた。
「我々、国家の政治を担うべき者が忠誠を誓うのは、国家でもなければ将軍でもなく、国民であるべき——私はその信念に、真に従うべきが来たと、十分に理解しているつもりだ」
「それは、つまり」
慎重に進言するつもりだった言葉を、先に目の前の小栗が自ら口にしたことに津田は驚きながら、先を促す。
「すでに将軍には話を通してある。将軍後見職・一橋慶喜殿にも理解を頂いており、すでに大勢は決しておる。国民の声が、政治の主導権を我々幕府から離すことを望まれた。で、あれば我々は——」
小栗はその後に続けるべき言葉の重みを嚙みしめるようにして、一拍を置いた。
思えば、彼は彼の自由意思においてすべての道を歩んできたようでいて、一方で彼は抗い難き時代の奔流のただなかに飲み込まれながらここまで来たのかもしれない。
それは、一つ一つは目の前の難局を打開するために必要な、必然の道であった。しかしそれは260年以上に亘る巨大な歴史に対する、一人の矮小な人間にとってはあまりにも重大な決断であったのだ。
(だが、なればこそ、私はこの「時代の流れ」を導く男とならん。かつての寺内殿のように——私もまた、時代に求められた改革者となるのだ)
そして、小栗はその言葉を告げた。
「我々幕府は、大政を陛下にお返ししよう。併せて、武家の棟梁としての、征夷大将軍職についても後ほど将軍より辞職の意を表されるであろう。江戸幕府は、これにて終焉を迎えることとなる。幕府一同、これに同意致す」
--------------------
老中首座・小栗忠順から提示された、幕府の政権を天皇に返上するとの意志は、将軍・徳川家茂の手による上奏文という形で正式に朝廷の下に届けられた。
そして令徳3年10月15日(1874年11月10日)、上洛した家茂を交えて開催された朝議にて、この上奏文の受理が決定される。朝廷はただちに十万石以上の諸大名に上洛を命じ、10月22日(11月17日)からはこれまで江戸にて開催されていた参与会議が京都にて急遽開催されることが決まり、公議派を中心として今後の日本の行く末を定める会議がおよそ1ヵ月に渡って続くこととなった。
そして令徳3年12月9日(1875年1月3日)。
公卿の岩倉具視の手により「王政復古の大号令」が宣言され、正式に幕府の廃止が決定。政治の主導権は、ついに天皇陛下の手に渡ったのである。

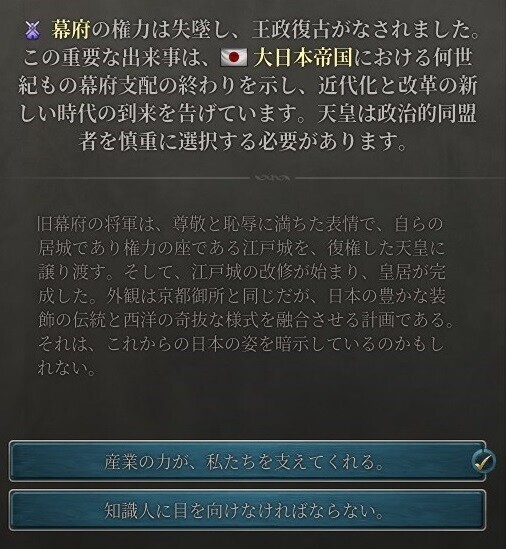

とはいえ、「公議派」が支配する参与会議が引き続き具体的な行政の主導権を握ることとなる。その総理(党首)として新たに「改革者」平岡宗悦が選ばれ、彼が王政復古後の最初の「総裁」として行政の最高責任者となった。

平岡の主導の下、参与会議は矢継ぎ早に次のような改革を重ねていくこととなる。
- 国号を江戸幕府から新たに「大日本帝国」へと変更。
- 一世一元の制を定め、令徳4年を「明治」元年と定めた。
- 旧来の身分制度を廃止し、四民平等を実現。「武士」階級も新たに士族と名前を変えつつもその特権は悉く廃止され、「侍の時代」の終わりが告げられることとなった。



そしてもう1つ、重大な改革が為された。
それは、選挙権こそ広く国民に行き渡る制度が10年近く続けられながらも、被選挙権は国民一般にはなく、引き続き国民の「代表者」が限りなく狭い「参与」たちに預けられていた現行の「参与会議」制度の廃止。
新たに立法府を「二院制」とすることが定められ、勅任議員によって構成された定数251名の「貴族院」と、直接国税15円以上を納める30歳以上の男子すべてに被選挙権を認めて選挙によって選出される定数465名の「衆議院」とに分けられることとなった。
そしてこの「衆議院」を構成する議員は先の改革によって結成が認められた「政党」が担うこととなり、明治4年(1878年)に実施されることが決定した第1回衆議院議員選挙に向けて各政党が鎬を削っていくこととなる。
そして1878年3月22日。
新たな選挙制度の下行われた第1回衆議院選挙では、商人・実業家たちを中心に支持を集めた「立憲政友会」が過半数の議席を獲得して勝利。

政党運動が巻き起こった当初に結党された自由民権派の立憲改進党・自由党らは、その後の内紛や激化事件によって当初の勢いを急速に失っており、一方で被選挙権が公家・大名以外に拡大したことは、経済力を持つ一部の実業家・地主たちに有利に働くことに繋がり、彼らの支持を集めた立憲政友会が最初の選挙戦を制したのである。

さらに、時代の変革の波に取り残され、その特権も剥奪されつつあった旧幕府・大名・武士勢力も結集し「立憲帝政党」を形成。
立憲政友会の勢いには大きな差をつけられてはいるものの、その中心に立つとある男が国民の支持を集めつつあり、彼を中心として「大日本帝国」は新たな時代を迎えようとしていた。

威信のとき
征韓論
明治10年(1884年)3月。「御一新」から実に10年の月日が流れ、江戸幕府改め大日本帝国は大きな変革を遂げつつあった。
都市部の市議会議員・商業会議所の会頭・会社社長・弁護士・銀行頭取、そして地方の地主たちといった社会的成功者たちを中心に支持を集めていた立憲政友会政権は、商工業と産業の発展を政策の軸に据え、江戸改め東京と称された首都には各地から鉄道が入り込み、急速な勢いで発展しつつあった。

東京の街中には洋装に身を包んだ裕福な「資本家」階級たちの姿が目に付くようになり、彼らはイギリスやフランスで作られた高級家具・衣類などを愛用する一方、自身の所有する工場で技能類稀なる職人たちに作らせた工具類を輸出することで莫大な富を築いていた。


それは土地貴族を中心とした封建社会からブルジョワジーを中心とした資本主義社会への変革による「光」の一面ではあったものの、一方で資本主義社会ゆえの「影」の側面も急速に拡大。
その典型的な帰結である貧富の差の拡大は広がる一方であり、たとえば大阪の町には50万を超える数の失業者たちが溢れかえり、彼らは日々を生きるのにも必死な様子を見せていた。

彼らの不満はやがて、民主主義の興隆を夢見ながら結果として一部の富裕者にその果実を奪われてしまった自由民権派勢力、そして特権を奪われ時代の変革に置いていかれつつあった旧幕府・大名・武士勢力の不満と結びつき、立憲政友会政権にとっても無視できない規模へと成長しつつあった。
そして、そんな「反政府勢力たち」の中心に、その男はいた。
西郷隆盛――元薩摩藩士にして、藩主・島津久光に従い攘夷派の実力者として幕末を戦いつつ、公議派が実権を握った新政府政権からの離脱ののちは、権利を失った武士・華族たちの擁護者となって新たな戦いを継続していた。

立憲政友会政権も彼らの「火種」を放置しているわけにはいかなかった。
西郷の旧知の仲でもある浜崎首相自らその説得に赴き、融和を図ることとなる。
----------------------------
「浜崎どん、我らん要求はただ一つじゃ」と西郷は対面した浜崎に対して静かに語り始めた。
「我ら武士ん誇りを、時代ん変化じゃとか何とかで汚さんでくれちゅうことじゃ。先日施行された廃刀令とやらも、あれは本当にひでもんじゃ。
もちろん、理解はしちょい。だが、現実ん武士たちを見じゃ。彼らん多くは農民となり、あるいは町民となり、それなりに苦労しながらも細々と小さな満足で過ごせちょっ者もおっじゃろう。一方で、軍人として残り、そん切なか誇りを大切にしちょっ者たちもおる。おいは彼らを見捨てたくないだけなんじゃ。同じ薩摩ん人間ならば、そん気持ちもわかっじゃろ」
西郷の言葉は静かで、穏やかに浜崎へと届けられる。しかしその言葉の芯には力強い威圧感が込められており、その広い背中の向こうには、何千何万という彼に付き従う士族たちの姿が見えるかのようであった。
彼は決して浜崎を、政府を脅しているような言い方はしていなかった。しかしそれは実質的に、政府から選択肢を奪うものでもあった。
「分かっちょい。武士ちゅう形を残すことを我らもすっわけにはいかんが、そいでも軍人として戦うてくれるわいたちを無下にはせん。近う、活躍ん場を与ゆっことを約束しよう」
「朝鮮、と?」西郷の言葉と鋭い眼光に、浜崎は押し黙る。それを肯定と受け取った西郷はしたり顔で続ける。「よかじゃろう。おいたちも兼ねて主張しちょった政策じゃ。奴らは国交を望む我らん使者を拒否したばかりか、我らを夷狄・禽獣とさえ呼んだち聞く。もはや御恩徳さえ与ゆに値せん。武力でもって即刻教化し、臣従せしめることが相応しかじゃろう」
そう言うと西郷はやおら立ち上がった。
「どけ行く気じゃしか?」
「決まっちょっじゃろ。早速、侍たちを訓練しけ行っど。彼らもしばらくん間、なまっていたじゃろうでね」
そう言って一国の首相に堂々と背を向けて向こうへと消えていく西郷の姿を見送りながら、浜崎はしばし頭を抱える。
扱いに困る奴らではあるが——しかしまあ、頼りになるのは確かだ。事実、朝鮮は今後のこの国の発展においては無視できない土地であり、列強と真に肩を並べるにあたり、それはいつか必ず手中に収めておくべき国であろう。

だが、その国の背後にはその宗主国たる「清」の存在があり——さらに言えば、南下政策を進める列強の一角、「ロシア」の姿があることもまた、事実であった。

この10年、培ってきた国力はある意味で、この瞬間のためにあった。
「御一新」から10年――大日本帝国は、いよいよ「世界」へと立ち向かう時を迎えることとなる。



日露清戦争
明治11年(1885年)1月1日。
大日本帝国は朝鮮国王・憲宗に向けて大日本帝国への臣従を要求。これに従わなければ武力による解決も辞さないという事実上の最後通牒を突きつけることとなる。

憲宗、およびその同盟者・大院君はすぐさま宗主国・清に支援を要求。清もすぐさまこれに応え、参戦を表明する。

さらに、この地域に影響力を及ぼしたいと考える列強・ロシア帝国が介入を宣言。

大日本帝国と貿易協定を結ぶイギリスは直接的な介入を見送りはしたものの、日本に最新式のアームストロング砲を大量に輸出することに決め、間接的に支援することを約束してくれた。

さらにイギリス人技術者たちも大量に日本入りを果たし、特に四国・高松において彼らの知識と技術を結集した最新式の武器工場を増設。


最新式の大砲とライフル銃とを大量生産し、来るべき戦へと備えることとなった。
そして明治11年(1885年)4月21日。
豊臣秀吉による朝鮮出兵以来実に300年ぶりとなる対外戦争の火ぶたが切って落とされることとなる。

まずは制海権を確保すべく、肥田提督の指揮の下、日本海にて朝鮮海軍たちを次々と壊滅していく。

肥田提督の活躍によって獲得した制海権を利用し、同年12月、日本陸軍総司令官・山縣有朋大将が半島東部から決死の上陸戦に挑む。


この上陸戦は見事成功し、山縣大将率いる10万の兵が朝鮮首都・漢城へと迫る。

清も援軍を送ってはくるものの、最新式の大砲を揃える大日本帝国陸軍に対し、旧式の武器しか用意できていない清の軍隊はもはや敵ではない。

今や東アジアの覇者に相応しいのがどの国であるかを明確に突きつける戦況であった。
とはいえ、司令部も楽観視していたわけではない。
むしろ、本当の戦いはこれからである。
開戦から1年。
いよいよ、列強・ロシア帝国の誇る「バルチック艦隊」が、長い旅路を終えてこの日本へと迫ってきているという報が、大本営には届けられていたのである。

日本海海戦
「どげんな? 準備は万全け?」
陸軍大将として山縣将軍と共に朝鮮入りを果たしていた西郷隆盛は、占領した釜山の港にて来るべき海戦に向けて訓練を繰り返していた帝国海軍司令長官・東郷平八郎に声をかけた。

「ええ、やれることはやり尽くしているつもりです。とはいえ、最新式の装甲船を用意しているバルチック艦隊に対し、我が海軍の中心は未だ木造の帆船。数だけは敵の2倍はあるにしても、綿密な戦策が肝要となります。油断はできません」

「なに、心配しすぎることも良うなか。わいん才能をおいは知っちょい。わいはだいよりも、もしかしたら世界のだいよりも優れた海ん英雄であり、誇るべき薩摩の名将じゃ。どんと構え、部下たちを安心させ、意気揚々と戦果を上げてけ」
西郷の言葉に東郷ははにかんだような笑みで応える。
東郷にとって、西郷の存在は単なる郷里の英雄というだけではなかった。10年前、彼が強く望んだイギリス留学が実現したのは西郷の助力あってのものであった。留学中、廃刀令の施行などを通して次々と追い込まれていく旧武士勢力が各地で反乱を起こそうとしていたとき、首相・浜崎太平次と交渉し軍人たちの権利を保証させたのもこの西郷の功績であった。東郷の実兄・小倉壮九郎も、その西郷の行動がなければ無謀な反乱に加担し、戦死するか捕らえられて刑死するかのいずれかであっただろう。
その西郷が切り開いてくれた軍人の誇りの可能性を現実のものとすべく、この一戦は決して失敗のできないものであった。
明治12年(1886年)6月13日。
東郷は釜山沖に現れたノルウェー汽船「オスカル」艦長から、4日前にフィリピン沖でバルチック艦隊と遭遇し、その士官から対馬海峡へ向かうと聞いた、という情報を手に入れる。
翌日に東郷は軍議を開き、間もなく行われるであろう日本の命運を決する一大決戦に向けた最後の準備を整えていった。
そして、6月27日午前2時45分。九州西方海域にて怪しい灯火を発見したという特務艦隊隊長の報告を受け、東郷はただちに各艦隊に集合を命じた。午前6時35分、それぞれの港から発艦した総勢88隻の帝国海軍が、バルチック艦隊の進路を阻むようにして、対馬海峡へとその姿を現した。
東郷は自らの乗る旗艦にZ旗を掲げさせた。
「皇國ノ興廢此ノ一戰ニ在リ、各員一層奮勵努力セヨ」
バルチック艦隊司令長官ピョートル・ロジェストヴェンスキー少将は目の前に広がる大日本帝国海軍のその数の多さに一度驚きはするが、一方で彼らの大半が木造の戦列艦であることも確認し、自信を取り戻す。麾下の全艦隊に臆せず敵艦隊に向けて前進するよう指示を出し、全39隻のバルチック艦隊装甲艦・モニター艦連合艦隊はゆっくりと帝国海軍のテリトリーへと近づいていく。
両者の距離が約7海里にまで近づいたとき、東郷は全艦隊に散開を命じる。88隻の帝国海軍はただちに海の全面を使用するが如く広がり、それはバルチック艦隊39隻を包み込むかのような陣形を見せることとなった。
ロジェストヴェンスキーは驚いていた。日本海軍は、その数の有利を活かし、正面から撃ち合いを挑んでくると思っていたからだ。バルチック艦隊の主力であるモニター艦は、「筏の上のチーズボックス」と揶揄されることもあるような異質な姿形をしているものの、極端に小さい標的面積と、そこに集中させた装甲による防御力とで、砲撃の撃ち合いであれば圧倒的に有利であるはずだった。

しかし日本海軍は正面からのそれを避け、艦隊を散開させた。
「モニター艦の特性を知っているのか? 厄介だな」
ロジェストヴェンスキー少将は忌々しげに吐き捨てるが、それでも質的有利に何も変化はない。周囲を取り囲み、一方的に砲撃を浴びせるつもりだろうが、しかし結局は当たらなければ意味がない。事実、日本艦隊は間もなくそれぞれの船からの砲撃をバルチック艦隊へと浴びせかけるが、いずれも艦隊の「チーズボックス」に掠りもしなかった。
そして向こうからバルチック艦隊の両脇に展開してきてくれたことは、バルチック艦隊にとってはありがたいことであった。すぐさま艦隊の砲塔を日本艦隊に向けて照準を合わせ、そこから次々と砲弾を撃ち放っていく。
しかしそれもまた、相手の艦隊に当たることはなく、水飛沫を上げるだけに終わった。そして大日本帝国艦隊はこれを避けるようにして再び散開し、今度はバルチック艦隊の後方を追いかけるような陣形を形成していった。
(なんだ? 何を考えている?)
海原を自由自在に、しかしその意図を読み取れぬ動きで展開していく日本艦隊に対し、ロジェストヴェンスキーはうろたえ、次の指示を出しあぐねてしまう。
そんなロジェストヴェンスキーの下に、新たな報告がやってくる。
「提督! 前方に日本艦隊の姿が!」
見ると、すでに散開し終えていたはずの前方の海域に、再び日本海軍の戦列艦の姿が現れていた。
さらに、
「提督! 両脇からも再び敵艦隊が!」
こちらも、先ほどの艦隊が離れた海域に、新たな敵艦隊の姿が、しかも先ほどよりもずっと多く、現れる。
「提督! 両脇の艦隊がまっすぐこちらに向かって来ています!」
「提督! 前方の艦隊もです!」
次から次へと飛び込んでくる信じられない報告に、ロジェストヴェンスキーの思考は止まってしまう。何をする気だ? 突っ込む気か!?
高速でバルチック艦隊に肉薄しようとする大日本帝国海軍の「両脇の部隊」。バルチック艦隊が砲塔を向け、迎撃しようとしたそのとき、彼らは再びその船頭を回転させ、花が開くようにして両脇に展開する。
そして置き土産のようにして、その側面から大砲が発射される。それらはほとんどがバルチック艦隊の船に当たることはなかったものの、そのうちのいくつかが、「チーズボックス」に命中し、確かなダメージを与えてしまう。
「反撃だ! 反撃だ! 1つでも多くの敵艦を沈めろ!」
ロジェストヴェンスキーの言葉を待たずしてバルチック艦隊は次々と砲を放っていき、これに直撃したいくつかの日本艦隊の船が撃沈される。しかし次の瞬間には彼らはまたその海域を離れ、遠くへと去っていってしまう。
かと思えば、
「提督! 前方の艦隊がこちらに!」
前方に現れていた日本艦隊が今度はまっすぐバルチック艦隊の隊列の先頭へと近づいていき、その直前で両脇に開き両艦隊は水平に交わる形で交錯する。
まるで曲芸を見ているかのような艦隊指揮。しかし、見惚れているわけにはいかない!
経験したことのないような戦闘の推移に砲撃手たちが戸惑い、砲を放つ手が止まった隙に、日本艦隊はすべて予定通りであるかのようにーーそして実際にそれは予定通りだったのだろうーー出会い頭に次々と大砲を放っていく。

恐ろしいほどの至近距離で放たれたそれらの砲撃は、チーズボックスの頑丈な装甲をも貫通し、何隻かのバルチック艦隊の船が沈められていく。
「提督! 被害の報告をーー」
「いらん! 全速力でこのまま前進しろ! とにかくこの海域から逃れるのだ! 元より我々の戦略目標は敵艦隊の殲滅ではなく、ウラジオストクへと到着し太平洋艦隊と合流すること。数的不利さえ埋められれば敵ではない。とにかくこの、馬鹿げたサーカスから一刻も早く抜け出さねばーー」
ロジェストヴェンスキーの言葉は、若い索敵手の悲痛な叫びによって遮られた。
「前方にみたび敵影を発見せり! その数・・・数十! 数え切れません!」
ロジェストヴェンスキーは力無く腰を下ろし、体の力が抜けるのを感じていた。
5時間以上にわたり繰り広げられたその海戦は、結果だけ見れば互いに大きな損害を与える結果にはなったが、バルチック艦隊の視点からすれば自由自在に動き回る理解不能な日本艦隊の「群れ」に一方的に蹂躙された思いであった。


ほうほうの体で日本海軍の「殺し間」を抜け出したバルチック艦隊は、当初の39隻からわずか9隻のみが生き残り、かろうじてウラジオストクに到着。

しかしこの海戦の惨状がロシア海軍にとってはトラウマとなり、以後、彼らはこの海で好きなように動くことはできなくなってしまった。
日本海は大日本帝国海軍の完全なる「庭」となったのだ。
終戦
補給の心配がなくなった朝鮮半島上陸軍は次々と朝鮮・清連合軍を陸戦で打ち破り、その占領地を広げていく。

シベリア鉄道を使って遅ればせながら到着したロシア陸軍の攻撃に対しても、「防衛戦略家」渋沢成一郎将軍がこれを迎え撃ち、圧倒的な物量差で撃退していった。

頼みの綱のロシア陸軍も歯が立たないと分かると、これ以上の継戦に意味がないと判断した清国は明治13年(1887年)6月に降伏。

同様にロシア帝国もまた、陸海共に敗北を重ね、国民の戦意は喪失していた。

とは言え、大日本帝国もまた、限界であった。
先の日本海海戦では8,000人もの英雄たちが海に散っていった。
開戦から2年4か月の間に積み上げられていった亡骸の数は28万を超えるほどとなっている。

陸軍総司令・山縣有朋将軍も、海軍司令長官・東郷平八郎提督も、これ以上の戦争継続は困難であるとの認識を示していた。
彼らの意見を容れ、浜崎首相はロシア帝国との和平の道を探り始めた。

かくして明治13年(1887年)8月6日。
日本の下関で結ばれた下関条約によって、ロシア・清の両国は朝鮮国の宗主権が日本にあることを認め、朝鮮が日本の保護国となることが正式に認められた。

一方で、日本はこの条約においてロシア・清に対し土地・賠償金の類を一切求めないことを約束。
この事実は、長く苦しい戦争の間、特別税による困窮や友人知人家族を喪う悲しみに耐え抜いてきた国民の怒りを激しく買うこととなり、条約締結の翌日には東京・日比谷の公園で大暴動が発生。内務大臣官邸や警察署が襲撃されるなど、激しい騒乱が巻き起こることとなった。

この事態を受けて、第一回帝国議会選挙以来政権を担ってきた浜崎内閣は総辞職し、同じ立憲政友会の大倉喜八郎が新たに首相に就くことに。

いずれにせよ、戦争は終わった。
日本にとって、初めて欧米列強と互角に渡り合い、そして実質的な勝利を得ることとなったこの日露清戦争。
その事実は瞬く間に世界中に駆け巡り、極東の小国と侮っていた日本という国の存在感を世界に知らしめることとなったのだ。
とくにその勝利の立役者となった東郷平八郎は、「東洋のネルソン」として称えられることとなる。
それから10年。
明治22年(1896年)5月4日。
大日本帝国はついに、「列強」の一角として認められることとなった。

寺内護久の改革から60年。これを継承した小栗忠順も、時代の奔流の中に飲み込まれながら、次なる時代の英雄たちにその魂を繋いでいった。
変革の時代を生き抜いた男たちが夢見た「坂の上の雲」は、ついにその眼前へと迫るほどになっていたのである。
では、その先に見える景色とは?
史実とは異なる歴史を紡いでいくこの世界の「日本」。
その、激動の20世紀が始まる――。
次回、最終回。
「急」へと続く。
これまでのプレイレポートはこちらから
革命と改革のメヒコ100年史:新DLC「Voice of the people」で遊ぶメキシコ編
虹の旗の下で 喜望峰百年物語:ケープ植民地編。完全「物語」形式
パクス・ネーエルランディカ:オランダで「大蘭帝国」成立を目指す
強AI設定で遊ぶプロイセンプレイ:AI経済強化MOD「Abeeld's Revision of AI」導入&「プレイヤーへのAIの態度」を「無情」、「AIの好戦性」を「高い」に設定
大地主経済:ロシア「農奴制」「土地ベース課税」縛り
金の国 教皇領非戦経済:「人頭課税」「戦争による拡張なし」縛り
Crusader Kings Ⅲ、Europe Universalis Ⅳのプレイレポートも書いております!
アンケートを作りました! 今後の方向性を決める上でも、お気に入りのシリーズへの投票や感想などぜひお願いします!